持続化給付金の要件
持続化給付金の要件に「売上が前年比50%以上減った月」と有りますが、この売上は「事業収入」なのです。
法人の場合は、
「不動産所得」という概念がないのですべて「事業所得」となります。
売上が「雑所得」「給与所得」として申告していた人も、事業での売上だと書類で証明できれば支給対象となります。
個人事業主の場合は、
個人の保有する資産の運用と見られるので、株式投資などと同じ性質のものとみなされるのです。
そのため、個人事業主は対象外となり、第二次補正予算案でも対象外のままなのです。
所得の種類について、詳しくみていきます。
様々な所得の種類と所得税法とは
確定申告などを行う時は、税理士に任せていているのでよくわからないという個人事業主の方も多いと思います。
一言で「所得」といっても所得税法上10種類に分類されます。
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得
さらに、不動産所得については、「事業所得」「不動産所得」とに分けられます。
不動産所得が「事業」としてみなされるのは、
- 一般的は判断基準
- 実質的な判断基準
この2つの基準となります。
一般的は判断基準で「5棟10室」です。
これは、公務員が家主業を行う時に、副業かどうかの判断基準にもなるのです。
- 区分マンションなら10部屋まで
- 戸建てなら5戸まで
- 1棟所有なら部屋数が10部屋まで
実質的な判断基準では、
「営利性」「継続性」「企業遂行性」「精神的肉体的労力の程度」「人的・物的設備の有無」「職歴・社会的地位・生活状況」「生活の糧かどうか」「一般的に即行として認知できるか」
など、これらの点を総合的に判断して、社会通念上事業と言えるのかどうかで判断されます。
今回、ご自分の収入が事業所得に当てはまると思っても、
基本的に税額の動きがなければ、修正申告はできないのです。
救済措置創設の可能性があるのか?
大家業の場合、収入が減る原因としてあげられるのは、
- 入居者の家賃滞納
- 退去者が増える
- 新たな入居者がいない
大きくこの3点となります。
この内、入居者の家賃滞納については、「住宅確保給付金」や「家賃支援給付金」を利用します。
ただ、この給付金は、大家の為の給付金というよりも、入居者の家賃負担を減らす目的となります。
「住宅確保給付金」は給付金額の振込先が大家の口座なので、確実に大家のもとに入金されます。
しかし、新たに法案が通過した「家賃支援給付金」は、対象が事業を行っている人で申請した人に振り込まれます。
給付金を受け取った人が、家賃として使うのかどうかの保証は無いです。
家賃の滞納によって、収入が50%以上減った大家さんは、入居者のために「住宅確保給付金」の申請方法を教えてあげることにより、
滞納分を振り込んでもらう事や、保証会社を利用するようにする必要があります。
国会では、現段階では不動産所得が対象となる改正の見通しはないようです。
せっかくの給付金ですが、個人と法人の支給要件を一律にするのは、かえって不平等となります。
そもそも、確定申告の際の税務署のアドバイスによって、「不動産所得」として申告をしている人も多いですね。
フリーランスの方でも「雑所得」として申告していて今回の給付金の対象外となっている人も多いのです。
今回の給付金の申請は、ご自分の申告を見直すきっかけになったと思います。
自己責任として自分で調べて、納得して書類を作成・申告をするようにしないといけません。



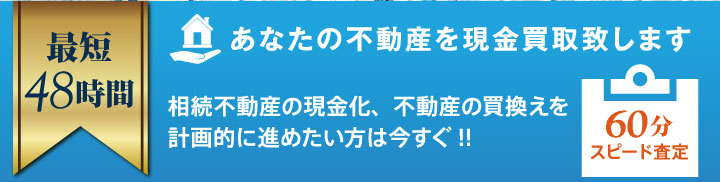
















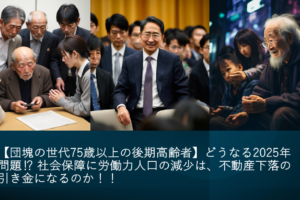
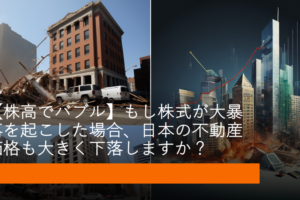



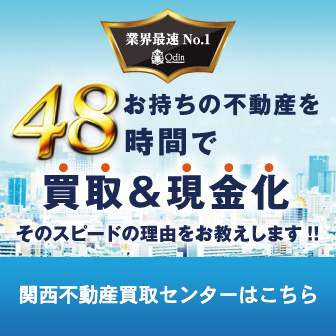
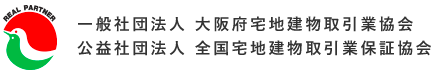




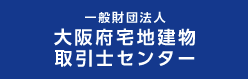


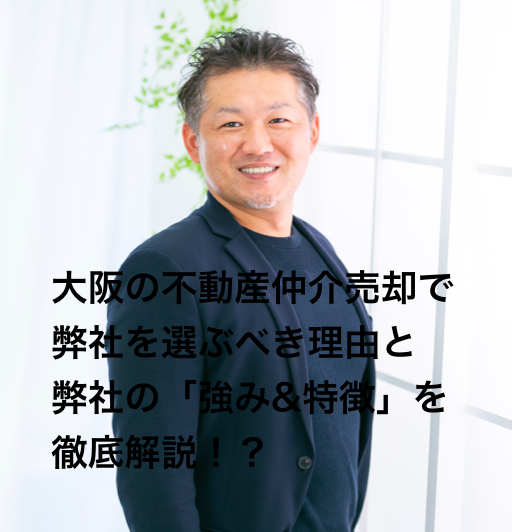
コメントを残す