不動産の売買を行った人にとっても、聞き慣れない税金ですが、「登録免許税」は、不動産の名義変更を行う際に必要な手続きです。
これは、法務局に不動産登記をした時に発生する税金です。
もしかしたら、あなたは支払っていることに気づいていないかも知れないかもしれません。
1.登録免許税を支払うのはどんな人?
登録免許税は、不動産の名義変更の手続きをした時に課せられる税金です。
主なのは、
- 不動産を買った時
- 不動産を相続をした時
- 不動産に抵当権を設定した時
- 不動産の抵当権を外す時
1,不動産と買った時というのは、不動産の売買を行った時は、一般的に買主が支払います。
登記費用に関しては、地域によって慣例が違いますが、買主が全額負担する地域も多いようです。
2,不動産を相続した時は、名義変更をしていない人もいるようですが、売買をする時に手続きが面倒になるために、相続した時にすぐ手続きをしましょう。
3,不動産に抵当権を設定した時は、金融機関が抵当権設定の登記を行いますが、費用を払うのは買主です。
ただ、一定の要件を満たす場合は、登録免許税の税率が借入金額の0.4%が0.1%に軽減されます。
4,不動産の抵当権を外す時は、売り主が負担となります。これは、他の権利の付いていない状態で買主に引き渡す義務があるからです。
ただ、借入金を完済していたとしても、自然に抹消されるものではなく、必ず所有者が行う必要があります。
2.登録免許税っていくらぐらいなの?
不動産の所有移転をする時に登録免許税を支払わないといけないのですが、
気になるのが、どれぐらい払うものかです。
特に、不動産売買を行う時は、売買代金以外にも諸費用がかかってくるので予算にいれる為にもどれぐらいか知る必要があります。
登録免許税は、国に収める税金なので、国税局のHPに算出法と表が掲載されています。


上の表のように、所有権移転の内容で、土地と建物とで税率が変わる場合もあります。
相続の場合は、土地・建物と共に不動産価格に税率(0.4%)を掛けた金額になります。(100円未満切り捨て)
ここでいう「不動産価格」というのは売買代金ではなく、【固定資産評価証明書】に記載された不動産の評価額となるのです。
不動産の所在である各市町村役場や市役所や区役所で取得することができますが、本人以外の場合は委任状が必要になってきます。
相続登記関しては、2018年の税制改正によって、2021年3月31日までは、土地の登録免許税は非課税となる場合があります。
3.登録免許税の支払い方について
登録免許税の支払い方は、大きく次の2通りの納付方法となります。
- 現金で納付
- 収入印紙で納付
現金で納付する場合でも、金融機関で納付してから登記申請書に領収書を貼り付けて法務局に申請するのですが、多くの人は、司法書士に依頼しているので、司法書士に支払う費用の中に含まれています。
司法書士の見積書には、これらの項目別に記載されています。
- 司法書士への手数料
- 通信費や手続きにかかった諸費用
- 登録免許税
司法書士に支払う金額だという認識で、自分が登録免許税を支払っていたと気づいていない人も多いのですが、司法書士に依頼していれば、きちんと支払われています。
収入印紙での納付は、3万円以下の場合は可能です。収入印紙は法務局や郵便局で購入する事ができます。
収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することが可能なのです。
銀行に納付したり、収入印紙を貼りつけて申請する場合も、自分で所有権移転の手続きを行う場合です。
司法書士に依頼しない分、司法書士への手数料分が節約になりますが、書類の作成や申請に時間と労力がかかり大変な作業となります。勉強と思ってやってみるのも良いかも知れませんが、法務局の相談窓口を活用してみて下さい。



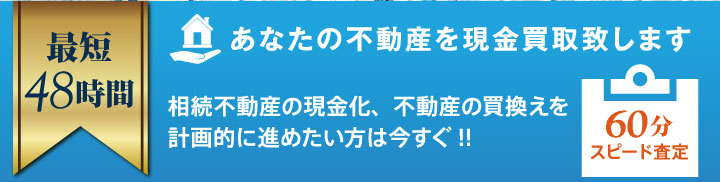























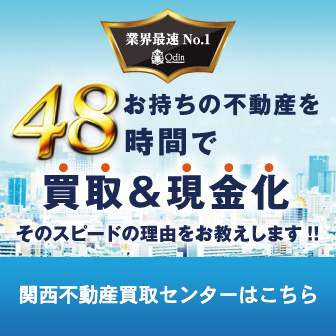
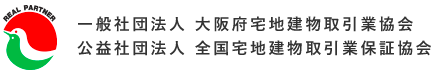




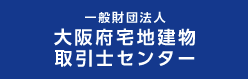


コメントを残す